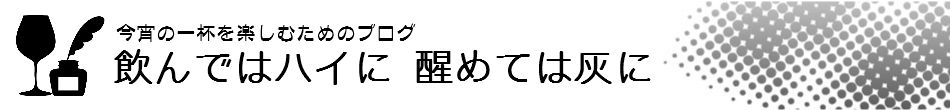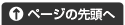ワインブログ 飲んではハイに 醒めては灰に
- » ワイン » ぶどうにも愛された丘 『サントリー登美の丘ワイナリー』
次に訪れたのはサントリー登美の丘ワイナリー。
150haという国内最大の葡萄畑を所有し、自社畑のみで運営する数少ないワイナリーでもある。
そしてこの登美の丘からは甲州市が見渡せる。その姿は圧巻だ。
登美の丘ワイナリーの歴史は深い。
そして日本のワイン史を語る上で避けては通れない人物が深くかかわっている。
必然、このブログは長くなる。
興味のない方は読み飛ばしてもらいたい。
その一人目は川上善兵衛(6代目)。日本のワインの父と呼ばれる。
川上善兵衛は1868年、新潟県に生まれる。
父の死後、6代目を継いだ善兵衛は川上家と交流のあった勝海舟の影響で葡萄栽培とワイン醸造を決意する。
そして品種改良を重ね日本初の醸造用品種、マスカット・ベリーAを開発する。
ワイン好きならかならず聞いたことのある品種のはずだ。
いまでも国内ワイナリーの多くがマスカット・ベリーAからワインを造りだしている。
甲州種と違い、その名からわかるように日本本来の土着品種ではない。
日本の気候風土に合わせて日本人が生み出したものだ。
そして二人目は鉄道参事官であった小山新助。
当時の中央線の工事は甲府まで伸びていた。そこで彼が目にしたのは太陽が降り注ぐ広大な高原。
1909年、小山新助はこの原野を買い入れ「登美農園」を開設する。
”登って美しい”から”登美”だ。
その後、この登美農園は帝国シャンパン、日本葡萄酒と複数の所有者のもとを渡り歩くが経営が上手くいかず廃園同然となってしまう。
最後の三人目は鳥井信治郎。サントリーの創業者であり、国産ウィスキーの父と呼ばれている。
1906年当時は寿屋洋酒店だったが、スペインから輸入したワインがまったく売れず、日本人の口に合うようにと赤玉ポートワインを生み出した。
(後にこの赤玉ポートワインが国産ウィスキーの発売の立役者となるのだが、それはまた別の話)
1921年には株式会社寿屋を開設。
当時の国産ワイン市場の60%を赤玉ポートワインが占めるというところまで成長していた。
役者は揃った。—そして始まりの年。
1936年に川上善兵衛と鳥井信治郎が登美農園の経営を継承。
寿屋山梨農場として立て直していくことになる。
1950年代にはワイナリーの中に研究所と学校を併設。
次世代の葡萄栽培家、ワイン醸造家を育てるとともに、葡萄栽培の技術を高めていった。
1954年には欧州品種であるメルロー、カベルネ・ソーヴィニヨン、シャルドネなど欧州品種の栽培を開始。
1975年には日本初の貴腐葡萄の収穫に成功した。
時は流れ1986年。
登美の丘で造った赤ワインの頂点「登美 赤」が誕生する。
1997年にはボルドーの国際コンクールで日本で初めての金賞を獲得。
現在に至るまで多くの優良なワインを生み出し、国産ワインをけん引してきた。
現在サントリーでは登美の丘を「ぶどうに愛された丘」と紹介している。
しかしそれはたぶん違う。
日本の風土に合う葡萄を生み出した男がいた。
葡萄の栽培に適した土地を見つけ出した男がいた。
日本人の口に合うワインを造ろうとし続けた男がいた。
誰が欠けても上手くいかなかったはずだ。
最初は「国産ワインを生み出そうとする人々が愛した丘」だった。そして葡萄はあとからやってきた。
『ぶどうに”も”愛された丘』がきっと正しい。
この記事を読んでいる人はこんな記事も読んでいます。
トラックバックURL